
11月5日は、
「津波防災の日」
元々2011年3月11日の
東日本大震災がきっかけで誕生した記念日なのです。
そう思うと
3月11日が津波防災の日になるのでは?
と思うところですが…
実はこの11月5日は
日本の歴史上こんな事があったのです。
【安政南海地震】
1854年12月24日。
旧暦では嘉永7年11月5日の事。
今の時間で16時30分頃、
”安政南海地震”が発生しました。
マグニチュードは8.5。
しかも地震の後には津波も押し寄せ、
被害は広範囲に渡ったと言われています。※南海地震と付くだけに、
今予想されている南海トラフ地震の様な大地震です)
ちなみに、
2日後には豊予海峡地震(M7.4)が発生し、
この年日本は2度の大地震に覆われたのです。被害は2つの大地震に襲われた事で、
実際にこの安政南海地震による被害がどれほどのものか、
はっきりとは判断できないそうです。
さらに翌年の1855年に
安政江戸地震(M6.9~7.4)も発生。この3つの地震を総称して
安政三大地震と言われています。
この安政南海地震の起こった11月5日。
これが「津波防災の日」になった理由です。
またこの大地震の出来事を
物語にした話があります。
・・・「稲むらの火」
地震の後に来る津波への警戒と
早期避難の大切さを語った物語があるそうなのですが
これが後々の危機意識向上にも役に立っているのです。
【 稲むらの火 】
舞台は紀伊国広村
(今でいう和歌山県有田郡広川町)ちょうど稲刈りの時期でした。
村の高台に住む庄屋の五兵衛は、
ガタガタという地震の揺れを感じます。そして五兵衛は
地震の後に来るとされる津波の兆候を感じ取ります。
心配になった五兵衛は、村人たちに津波が来る事を知らせようとします。しかし村人たちはちょうど祭りの準備で忙しく、
まったく津波が来ることを知らなかったのです。そして、
五兵衛は津波が来る事を知らせるため、
自分の田の稲の束(稲むら)に火をつけたのです。
それを見て火事だと思った村人たちは
一斉に火を消すため高台の方に駆け付けたのでした。
こうして村人たちは高い場所に移動でき、
津波から逃れる事ができたのです。
これは愛知工業大学が製作したものです。
この様にアニメにもなるくらいで、
今では子供達への教材としても利用されているそうです。
でも子供だけでなく、
大人が見ても結構深い話なのです。
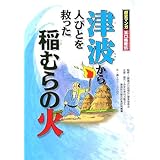 |
![]()


















